教会で「バケツ稲づくり」をはじめてみました その19
「一粒のお米をバケツで育てる」バケツ稲プロジェクト♪ 機関誌の「リジョイス」に掲載中の呼びかけに応じて「はじめてみた」を赤裸々に報告しています。 第19回目のタイトルは「脱穀」です。
「一粒のお米をバケツで育てる」バケツ稲プロジェクト♪
前回は稲を乾燥させている間ということもあって、
お米を育てるのにあたって外せない草刈りについて
ご紹介をしました。
さて、また本題に戻って今回は脱穀です。
脱穀とは稲からその実を取り出す作業のこと。
思い浮かべるのは千歯こきという櫛の大きな道具や、
唐蓑(とうみ)と呼ばれる風を送って籾を選別する道具です。
今は、まさにその名も「コンバイン」がそれらを一手に引き受けているそうです。
さて、そのような道具が一切ない場合にどうすればよいのか。
棒でたたく? 割りばしを使う??
色々調べてみた結果、一番手っ取り早かったのは
紙パックの再利用でした。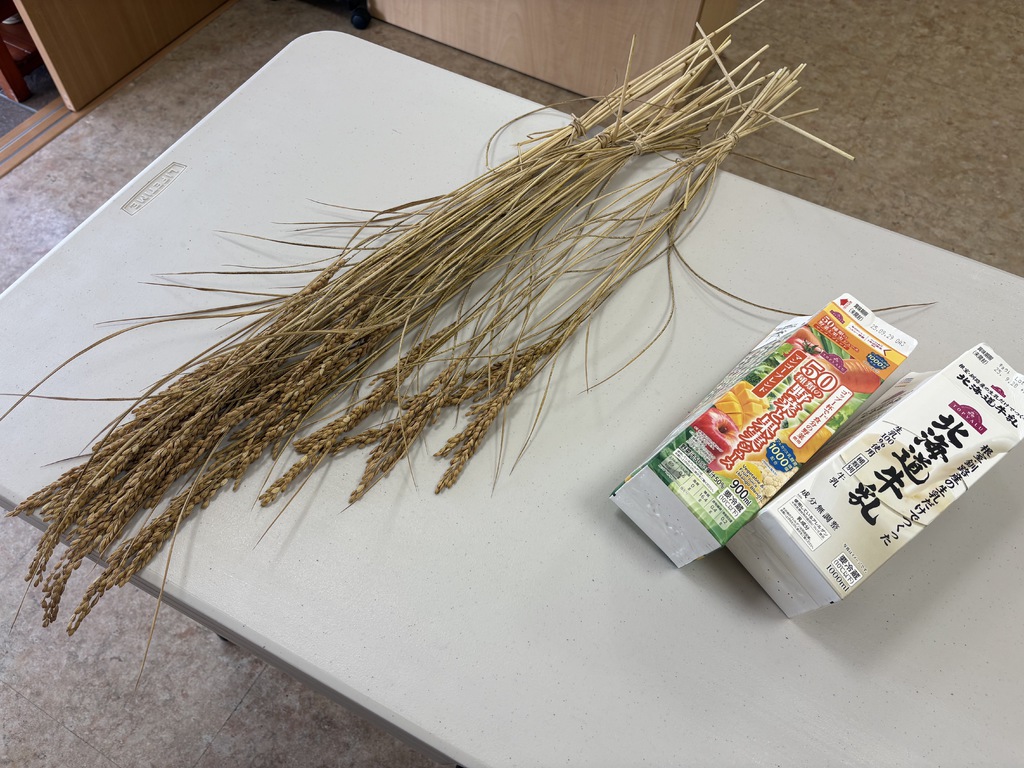
教会の皆さまと一緒にやってみました。
注ぐ口のところに稲を入れて挟み、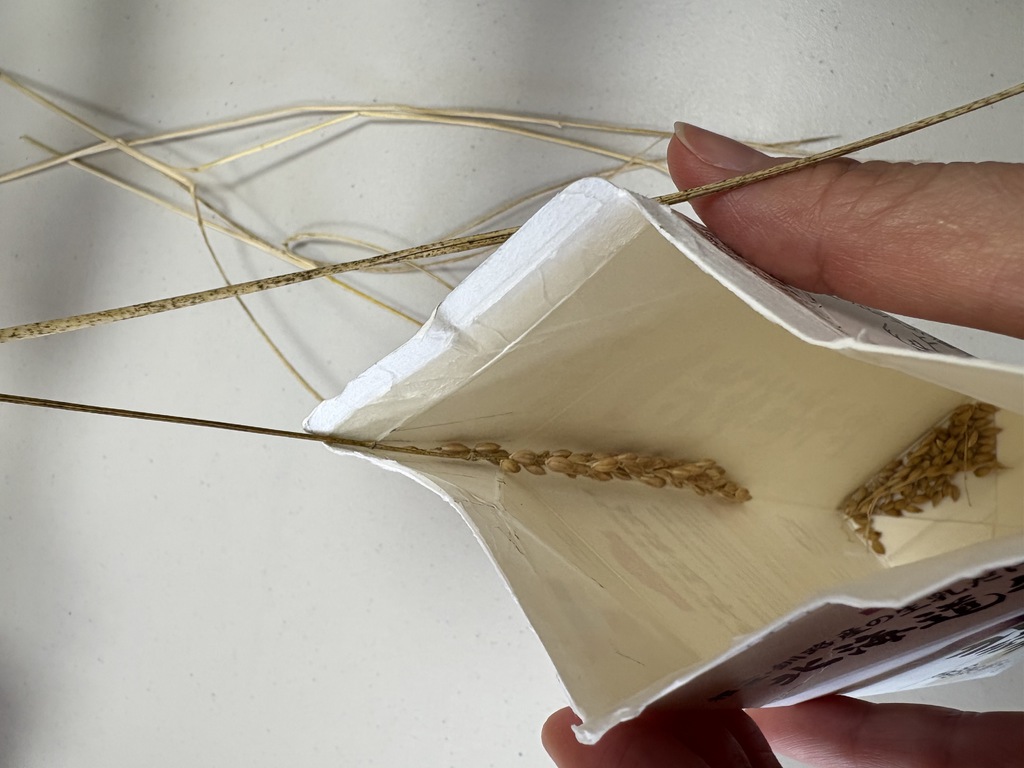
ひっぱると、パックの中にこぼれず穂先が残るという方法です。
私は途中でぶちぶち千切れてしまったのですが、
河内長老はとても上手に脱穀をされていました。
聖書でもたびたび登場するこの脱穀。
例えば「脱穀している牛に口籠を掛けてはならない。」
(申命記25:4)というみ言葉があります。
口籠(くつこ、またはくつご)とは、
藁や竹などで作られているいわばカバーで、
家畜が人を噛んだり、農作物を食べないようにする道具のこと。
聖書のころは、麦わらを円状に敷き詰めて、
ぐるぐると牛に踏みつけてもらう。
そのようにして脱穀がなされていたようです。
そして自分で脱穀をしてみて気付いたこと。
脱穀する牛がおもに口にするのは、わらのほうだろうということです。
もちろん麦もついているでしょうが、その体積比が違いすぎました。
(写真を取り忘れてしまいました、、、。)
さて次回は脱穀した種もみから玄米を取り出す「籾摺り(もみすり)」です。
次回もどうぞお楽しみに♪
※次回の記録はコチラから。
https://rcj.gr.jp/nishitani/news/detail.php?id=573
この記事に添付ファイルはありません
西谷教会の礼拝出席に事前予約などは必要ありません。しかし
「車で行くので駐車場の案内をしてほしいです。」
「子供連れで行きたいので母子室を利用したいのですが…」
「なるべく前のほう(後ろのほう)の席に座りたいです。」
などなど初めての礼拝出席において、あらかじめリクエストやご質問がある方は「礼拝参加予約フォーム」からその旨お伝えいただくと、当日の受付案内がよりスムーズに行えます。
