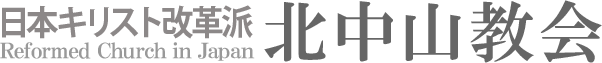世から選び出される
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ヨハネによる福音書 15章18節~25節
18「世があなたがたを憎むなら、あなたがたを憎む前にわたしを憎んでいたことを覚えなさい。19あなたがたが世に属していたなら、世はあなたがたを身内として愛したはずである。だが、あなたがたは世に属していない。わたしがあなたがたを世から選び出した。だから、世はあなたがたを憎むのである。20『僕は主人にまさりはしない』と、わたしが言った言葉を思い出しなさい。人々がわたしを迫害したのであれば、あなたがたをも迫害するだろう。わたしの言葉を守ったのであれば、あなたがたの言葉をも守るだろう。21しかし人々は、わたしの名のゆえに、これらのことをみな、あなたがたにするようになる。わたしをお遣わしになった方を知らないからである。22わたしが来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが、今は、彼らは自分の罪について弁解の余地がない。23わたしを憎む者は、わたしの父をも憎んでいる。24だれも行ったことのない業を、わたしが彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は、その業を見たうえで、わたしとわたしの父を憎んでいる。25しかし、それは、『人々は理由もなく、わたしを憎んだ』と、彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ヨハネによる福音書 15章18節~25節
今日、イエスは、これから何が弟子たちに起こってくるのかということをご存じの上で、弟子たちを安心させようとしておられます。
それが今日の最初の、「世があなたがたを憎むなら、あなたがたを憎む前にわたしを憎んでいたことを覚えなさい」。という御言葉です。
弟子たちはこれから、人々に憎まれるんですね。
その弟子たちに、これからそういうことがあったとしても、余計に驚くことはないよ、むしろ当たり前のことだと思いなさい、と言って、心の準備をしてくださっているんですね。
実際、弟子たちには、この後、迫害されるということが何度も起こってきました。
それは弟子たちだけではないですね。
キリスト教の歴史の最初の三百年間は迫害の歴史です。
日本でも、豊臣秀吉の時代から江戸時代に終わりまで迫害がありましたし、戦前戦中の時代にも、国家によって教会が監視され、天皇を神として礼拝しなかった人が逮捕されるというようなことがありました。
しかし、今の時代はどうでしょうか。
どう考えても、「世から憎まれる」というほどのことはないわけです。
しかし、今日の話は私たちには関係のない話ではありません。
イエスは次の19節で、どうして世が弟子たちを憎むのかを説明しておられます。
それは、弟子たちが世に属していないからです。
弟子たちというのは、イエスによって、世から選び出された者なんですね。
弟子たちは世から選び出されて、イエスに属する者となっている。
これは私たちも同じです。
英語のクリスチャンという言葉の元になった言葉はギリシャ語のクリスティアノスという言葉なんですが、このクリスティアノスという言葉は、キリストに属する者という意味なんですね。
弟子たちは世から選び出されて、キリストに属している。
だから、世には属していない。
だから、憎まれるんですね。
属していないからと言って憎むのは心が狭いと思われるかもしれませんが、19節に、「身内」という言葉がありますね。
この言葉は、原文では「自分のもの」という言葉なんですが、ここのところを読むと、世は、それが自分のものなら愛するということですね。
自分のものを愛する。
それはおそらく誰でもそうでしょう。
キリストも、弟子たちのことがご自分のものだからこそ、ご自分自身のように愛するわけです。
けれども、キリストの弟子は、世のものであったところから、キリストのものへと移された者なんですね。
もう、世のものではないわけです。
キリストのものです。
そして、今日の最初の18節で、「世があなたがたを憎むなら、あなたがたを憎む前にわたしを憎んでいたことを覚えなさい」と言われていました。
世は、まず、キリストを憎んでいたわけです。
そうなると弟子たちというのは、世にとっては、自分のものだったのに、憎んでいる相手に奪われて、自分のものでなくなったものですね。
ここでもし、弟子たちもキリストを憎んでいるのに無理やりこの世から拉致されて嫌々キリストのものとされたというのなら、世は弟子たちを憎むことはないでしょう。
でも、そうではないんですね。
弟子たちはキリストに愛されており、それを喜んでいるんです。
今まで、世のものであって、世が愛していた人々が、キリストのものとされて、キリストに愛され、それを喜んでいる。
そうなると、世はキリストだけでなく弟子たちも憎みますね。
その流れで、イエスは20節で、「『僕は主人にまさりはしない』と、わたしが言った言葉を思い出しなさい」と言われます。
この前の場面で、イエスにとって弟子というのは僕ではない、友だとおっしゃってくださいましたが、友だというのは、イエスがご自分のなさることを全て教えてくださるという意味で、僕ではない、僕というのは、主人が何をしているか知らないんだ、ということでした。
弟子たちにとってイエスは主人であるにも関わらず、イエスはご自分のなさることを前もって、すべてを教えてくださるんですね。
ただそれは、イエスと弟子たちが対等になったということではありません。
対等でないにもかかわらず、友として扱ってくださって、弟子にすべてを教えてくださっているということなんです。
イエスが主人であり、弟子は僕であることに変わりはありません。
そして、「僕は主人にまさりはしない」というのは当然と言えば当然のことですが、僕というのは主人に属する主人のものです。
ですから、「人々がわたしを迫害したのであれば、あなたがたをも迫害するだろう」ということになるわけです。
むしろ、そうならないのがおかしいわけです。
続けて、「わたしの言葉を守ったのであれば、あなたがたの言葉をも守るだろう」と言われています。
ここのところの主語は、この前後と同じ、「人々」です。
人々はイエスの言葉を聞かなかったのですが、もし、イエスの言葉を守ったのであれば、弟子たちの言葉をも守るだろう、ということですね。
そういうことはないわけなんですが、ここでは、イエスと弟子が一つであることが言われていると言えます。
似たようなこととして、13章20節でイエスは、「わたしの遣わす者を受け入れる人はわたしを受け入れ、わたしを受け入れる人は、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのである」と言っておられました。
弟子とイエスと神はリンクしているんですね。
そのようなことは、他にも言われていました。
14章20節では、「わたしが父の内におり、あなたがたがわたしの内におり、わたしもあなたがたの内にいる」ということが言われていました。
つまり、世の人々がイエスを憎むのは、世のものであったのにイエスのものとされたからなんですが、それは、この世の人々がそういう見方をしてくるということだけではなくて、イエスにとってもそれはそうなんですね。
この世もイエスも、同じ認識だということです。
その認識に立って、21節ですが、「人々は、わたしの名のゆえに、これらのことをみな、あなたがたにするようになる」ということですね。
憎み、迫害するようになるわけです。
そうなってしまう理由について、今までは、誰のものであるのか、ということが言われていましたが、イエスはここで、人々は「わたしをお遣わしになった方を知らないからである」と言うんですね。
「わたしをお遣わしになった方を知らないからである」というのはどういう意味でしょうか。
神がイエスを遣わしたことを知らないということですね。
これは、知らないというより、認めなかったと言った方が分かりやすいところです。
認めた人もたくさんいたわけですが、結局この後、人々は皆、「十字架につけろ」と叫ぶことになります。
どうしてかというと、人々は、支配者であるローマ帝国から自分の国を救い出してくれるのが救い主だと信じていたからなんですね。
救いと言ったらローマ帝国からの救いだったわけです。
ローマ帝国を打ち倒すような力のある人がローマ帝国に逮捕されるとは思いませんから、十字架につけろと叫んだんです。
支配されている人たちにとって、支配からの解放というのは重大なことです。
そのような状況にあって、自分たちは神が選んだ神の民だということを誇っている人々が、何よりもまず、外国の支配から救い出されることを求める気持ちは分かります。
けれども、イエスはもっと重大なことをなさってくださいました。
外国の支配から救い出すのではなく、罪の支配から救い出すんですね。
神が選んだ神の民とは言っても、人々は皆、自分に罪があるということは知っていました。
だから、罪を犯さないように、聖書の言葉に基づいて生きることを心掛けていたんですね。
けれども、そのように一生懸命真面目に生きている人だからこそ、罪を指摘されると受け入れられません。
誰だって、自分が正しいと思いたいわけです。
実際、正しく生きていると思っているわけです。
それどころか、神が選んだ神の民だということを誇りに思っているんです。
だからこそ、受け入れられない。
旧約聖書に預言書というのがたくさんありまして、これは神から言葉を預かって、それを人々に伝えた人たち、預言者という人たちの書いた本なんですが、預言者たちの言うことというのは、結局のところ皆同じですね。
人々の罪を指摘して、悔い改めなさいということです。
しかし、そのようなことを言うと、預言者は必ず、人々から迫害されました。
驚くようなことではありません。
イエスは、旧約聖書の預言者たちが受けたのと同じ扱いを受けたというだけのことです。
ただ、イエスは死刑にされただけではありません。
イエスは人の罪を背負って、罪に対する罰を、代わりに受けてくださったんですね。
ですので、裁判の場でも何も言わなかった。
ご自分の役割を知っておられたからです。
そしてこれは、預言者にはできないことでした。
預言者が迫害されて殺されても、その人一人が死んだということにしかなりません。
預言者には、誰か他の人の代わりに罪に対する罰を受けることはできません。
イエスは神であるからできる。
というよりも、そのために、神は神の子を人とならせて、罪人の手に委ねてくださったのです。
神の民が外国に支配されているという状況は、確かに重大なことです。
しかし、罪が人を支配している状況とは、比べられません。
罪が人を支配しているということは、人は神にふさわしくないということであり、人はいつか、裁きを受けて滅ぶしかありません。
それはひどいではないかと思うかも知れませんが、神がそう決めたことです。
そして、罪には裁きをというルールは私たちも当然のこととして認めていることです。
もとより、神は、すべてのものの造り主です。
時間を造り、空間を造り、すべてのものを造り、それらを支えるすべての法則を造ったのも神です。
神がルールなんです。
スティーブン・ホーキング博士は、宇宙と物理法則が人間のために設計されたように見えると語っています。
「宇宙と物理法則は、私たちのために特別に設計されているように見える。
もし、約40種類の物理法則のうち、どれかたった1つでも、ほんの少し異なる値を持っていたら、私たちが知っているような生命は存在できない。
原子が安定しない、原子が結合して分子になることができない、生命が誕生する前に宇宙が崩壊してしまう、など様々な問題が起こる」と言うんですね。
すべてにおいて、絶妙な秩序があるんですね。
宇宙は特別に設計されているんです。
それを造ったのが神です。
このような絶妙な秩序をお造りになった方の前で、反論などできません。
罪には裁きが降ります。
言ってみればそれも法則です。
ただ、その裁きを、神の子が人となられて、人の代わりに受けてくださったのです。
これほど重大なことは他にありません。
ただ、人々は罪に定められます。
22節ですが、「わたしが来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが、今は、彼らは自分の罪について弁解の余地がない」ということですね。
何も知らなかったら、罪にはならないんですね。
ですが、イエスは来て、彼らに話しましたから、もう弁解できない。
逆に言うと、分かろうとすれば分かったはずだということですね。
でも、分からない。
それはつまり、最初から認めないと決めていた、ということです。
イエスが来たことで、それが明らかになってしまった。
その罪が明らかになってしまったんですね。
しかし、最初から認めないと決めてしまうことは問題です。
それは、自分を主にしているということになるからです。
そうなると当然、イエスも神も主になりません。
最初から認めないと決めることは、自分を神にすることです。
それ以上の罪はないでしょう。
23節で、「わたしを憎む者は、わたしの父をも憎んでいる」ということですが、イエスを最初から認めないと決めている人は、神をも最初から認めないと決めていることになります。
イエスは神の御心の通りになさっているからです。
24節では、「だれも行ったことのない業を、わたしが彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は、その業を見たうえで、わたしとわたしの父を憎んでいる」と言われます。
イエスが奇跡を行わなければ、人々に罪はなかったんですね。
奇跡が起こらなかったのなら、信じなくても仕方ない。
しかし、奇跡を見た上で、神の御心を行っているイエスを認めない。
これも同じで、最初から認めないと決めていた、ということでしょうね。
それは言い換えると、最後の25節の、「人々は理由もなく、わたしを憎んだ」ということです。
そして、そのことは、旧約聖書の言葉が実現したことだったと言われています。
ただ、それもすべて、御手の内にあることだったということです。
神の御心は、人を救うことです。
だから、イエスは十字架にかけられなければなりません。
そのためには、「人々は理由もなく、わたしを憎んだ」ということでなければならないんです。
「人々は理由もなく、わたしを憎んだ」ということは、十字架に至る必然であったということなんですね。
必然なら、罪があったとしても、責任を問わないでほしいと思うかもしれません。
これについて、山中雄一郎先生は、ウェストミンスター小教理問答の解説で、このようなことを書いておられます。
事件が起こった時、検察官は犯人の責任を調べます。
それに対して、心理学者は、犯人のそれまでの人生や、人生の中で形成されてきた性格を調べます。
これはいわば、犯人がそのような事件を起こした必然性を調べるということです。
必然なら責任はないはずですが、私たちは、罪には罰が与えられることを認めています。
このようなことを書いておられるんですね。
必然でも、責任は問われます。
ある意味、当たり前のことです。
罪というのは、前もってあったルールに違反することだからです。
必然だろうが偶然だろうが、前もってあったルールに違反すれば、罪に問われます。
しかし、もっとも重大なルールとは何でしょうか。
罪に対する罰を、イエスが引き受けてくださったということです。
それは、嫌々ではありません。
イエスが私たちをこの世から選び出し、ご自分のものとして愛してくださったからです。
そして、その愛と救いをいただくことは、ある意味で簡単なことです。
最初から信じないと決めつけなければいい。
自分を神にしなければいい。
それだけのことです。
それだけで、イエスはその人を選び出してくださいます。
イエスは人を裁くために来られたのではありません。
救うためにこられたのです。
そして、世のものとされ、罪に支配されていた私たちを選び出し、救いに入れてくださったのです。