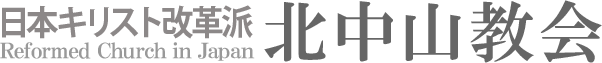マリアの喜び
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ルカによる福音書 1章46節~56節
46そこで、マリアは言った。「わたしの魂は主をあがめ、
47わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます。
48身分の低い、この主のはしためにも
目を留めてくださったからです。
今から後、いつの世の人も
わたしを幸いな者と言うでしょう、
49力ある方が、
わたしに偉大なことをなさいましたから。
その御名は尊く、
50その憐れみは代々に限りなく、
主を畏れる者に及びます。
51主はその腕で力を振るい、
思い上がる者を打ち散らし、
52権力ある者をその座から引き降ろし、
身分の低い者を高く上げ、
53飢えた人を良い物で満たし、
富める者を空腹のまま追い返されます。
54その僕イスラエルを受け入れて、
憐れみをお忘れになりません、
55わたしたちの先祖におっしゃったとおり、
アブラハムとその子孫に対してとこしえに。」
56マリアは、三か月ほどエリサベトのところに滞在してから、自分の家に帰った。
57さて、月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ルカによる福音書 1章46節~56節
前の場面で、マリアがエリサベトに会いに行った。
エリサベトはマリアの親戚。
マリアはまだ今で言うところの中学生くらいの年齢だが、エリサベトはもう子どもを生めないような年齢。
そのエリサベトが身ごもった。
マリアはそのことを天使から聞いた。
天使と聞くと現実的でない気分になるが、天使という言葉は原文では「メッセンジャー」という言葉。
つまり、神の言葉を伝える人。
なので、見た目の問題ではない。
天使と聞くと、白いふわっとした服を着て、背中に大きな羽が生えているイメージがあるが、聖書のどこにもそんなことは書かれていない。
天使が天使であるのは、神の言葉を伝えに、人に会いに来た、ということ。
逆に言うと、マリアが、その言葉を、神の言葉として聞いた、ということ。
マリアは、まだ結婚していないのに、あなたは男の子を生む、と聞いた。
その子は救い主になる、と聞いた。
考えられないようなその話を、マリアは、神の言葉として聞いた。
そして、そのマリアに、それが神の言葉であるしるしが与えられた。
子どもを身ごもるはずのない、年取ったエリサベトが身ごもったということ。
マリアはそれを聞いて、エリサベトに会いに行く。
そしてそこで、マリアは、エリサベトを通しても、また神の言葉を聞くことになった。
エリサベトはすぐ前の場面で、マリアを祝福した。
これはエリサベトが語った言葉だが、聖霊に満たされて語った言葉。
聖霊、神の霊がそう言わせた。
つまり、これも神の言葉だということ。
今日の場面の直前の45節でエリサベトがマリアに、あなたは幸いだ、と言った。
それを受けて、マリアが、私は幸いです、と返した。
それがこのマリアの賛歌。
マリアの賛歌は、「マグニフィカ―ト」と呼ばれて、オーケストラの曲になったりもしている。
「わたしの魂は主をあがめ、わたしの霊は救い主である神を喜びたたえます」。
この「あがめ」が「マグニフィカ―ト」。
意味は、「大きくする」。
私の魂は主を大きくする。
神様を大きくする。
逆に言って、自分を小さくするということ。
だから、48節で、「身分の低い、この主のはしためにも目を留めてくださったからです」。
「はしため」とは女性の奴隷。
マリアは奴隷ではない。
しかし、自分をはしためだと言って、その上で、神のことをここで「主」と呼んでいる。
「主」という言葉が聖書ではしばしば使われるが、原文を見ると、単に「主人」という言葉。
これは言わば日本語で言うところの謙譲語の表現。
自分を低くして、相手を高める。
当時一般に、大人の男性のことを「主」と呼んでいた。
私はあなたに比べたら、しもべのような者です、ということ。
へりくだった表現。
ここでは、マリアは、神が主人で、自分はその奴隷だと言った。
ただ、奴隷と言っても、私たちがイメージする奴隷とは違う。
私たちがイメージする奴隷は、2、300年前のアメリカの黒人奴隷。
人間扱いされていなかった、家畜同然の奴隷。
この時代の奴隷はそうではない。
主人は奴隷の面倒を見なくてはならない。
だから、自分から進んで奴隷になる人もいた。
例えば、親から財産を受け継いで、土地を持っていたり、お店を持っている人は、それを元手に仕事をしていけばいい。
しかし、十分な財産を持っていない人は、自分の労働力を販売して生活する、ということで、自分から奴隷になった。
自分のために働いてお金を稼ぐのではなく、人のために働いてお金をもらう。
要は、現代で言うところのサラリーマン。
自分の労働力を他人に販売して生活する。
聖書の時代の人々が、現代の日本にやってきたら、驚くだろう。
この国ではほとんど全員奴隷なのか、と驚くだろう。
そして、現代では、サラリーマンの面倒を会社が見なければいけないというのと同じように、この時代には奴隷の権利も保証されていた。
主人が奴隷の面倒を見なければならない。
奴隷は主人の言うままに働く。
その代わり、主人は奴隷の面倒を見る。
生活に必要な給与を与え、健康に働き続けられるように、休暇を与える。
つまり、マリアが、「わたしは主のはしためです」と言った時には、神様が私の面倒をすべて見てくださる、という気持ちも込めてそう言っている。
自分はその神様の御手の中で生きる。
だから、神様が自分に「目を留めてくださった」と喜んでいる。
そして、神様が目を止めてくださるのはマリアだけではない。
マリアは何も特別な人ではない。
今で言う中学生くらいの年齢の、ごく普通の女の子。
神様がマリアに目を止めて、私たちに目を止めておられない、ということはない。
確かにマリアは特別な働きをした。
イエス様の母となった。
それはもちろんマリアの力ではない。
49節に「力ある方が、わたしに偉大なことをなさいましたから」とある。
しかし、そのような「偉大なこと」はマリアにだけ起こることではない。
マリアは言っている。
48節後半「今から後、いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう」。
つまり、マリアは時代を超えて、幸せな人のモデルになるということ。
マリアはどういう意味でモデルか。
神のはしため。
自分を小さくして、神を大きくした。
それによって神に大きく用いられた。
そして、それはマリアだけのことではない。
自分を小さくして、神を大きくする。
当たり前といえば、当たり前のこと。
そして、それはこのような歌を歌うほど大きな喜び。
それが私たちにも起こると言われている。
50節に、「その憐れみは代々に限りなく、主を畏れる者に及びます」とある。
マリアだけではない。
いつの時代でも、神を信じる人は幸いな者となる。
これが神の約束。
では、私たちが幸いな者となると、どのようなことが起こるか。
51節から53節を読んでみよう。
「主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き降ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い物で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます」。
小さな者が大きくされ、大きな者が小さくされる。
神の前に小さな者が大きくされ、神をも恐れぬ者が小さくされる。
神の前に小さな者としては幸いなこと。
ただ、ここで言われているのは、自分一人のことではないということ。
自分を小さくして、神を大きくすることが自分にとっての幸いだが、その幸いが自分一人のことではなくて、自分の周りにも及んでいく。
自分の周りでも、小さな者が大きくされ、大きな者が小さくされるということが起こっていく。
これを、救いと裁きと言ってもいい。
そのような神の業が目に見えて現れてくる。
それは、神の約束だった。
54節に「イスラエル」とあるが、これは「神の民」ということ。
そして、55節に神の民のことが、「わたしたちの先祖」と言い換えられている。
その「わたしたちの先祖におっしゃったとおり」ということだから、これはそういう約束があったということ。
そして、55節には「アブラハム」というイスラエル人の先祖の名前が出てきている。
そして、そこに「とこしえに」、永遠に、とある。
昔からの神の約束は永遠に変わることがない。
神はご自分の前に小さな者を憐れんでくださる。
だから、私たちは、神の前に自分を小さくする。
神を主とする。
私たちは従。
そこに、神の御業が現れて、私たちは大きくされるという約束。
では、私たちは、どのように大きくされるのか。
クリスチャンの作家、アンデルセンの名作に『マッチ売りの少女』がある。
実は、アンデルセンの『マッチ売りの少女』は、これについて書いたものと言える。
大晦日の夜、マッチを売りに裸足の少女が出かける。
もし売れずに家に戻ったらお父さんにぶたれてしまう。
行き場のない彼女が、家と家の間の路地に入ってマッチを擦るとストーブに当たっているような気がした。
しかし、マッチが消えるとストーブの幻影も消えてしまう。
2本目のマッチを擦ると光の中にお金持ちの家の中が浮かぶ。
皆で楽しい夕食会。
しかし、マッチが消えるとこの情景も消え失せる。
3本目のマッチでは美しいクリスマスツリーが見えた。
何千本もろうそくがきらめいている。
しかし、マッチが消えるとろうそくの光はみんな空に上って星になった。
4本目を擦ると懐かしいおばあさんが光り輝く姿で現れる。
少女はおばあさんを何とか引き留めるために残りのマッチを全部束にして擦る。
明るい光の中でおばあさんは少女を腕に抱き上げ、高く高く天に上って行った。
寒さもひもじさもない神のみもとに連れて行った。
次の日の朝、一人の小さな少女は凍死していた。
口元には微笑みを浮かべたまま。
街の人々は教会で少女の死を心から悼み、教会で祈りを捧げるのだった。
この物語は日本では悲劇として語られることが多い。
幸薄き少女に心痛める話となってしまう。
ところがアンデルセンは原作の結びでこう書いた。
「少女がどのように美しい物を見たのか、どんなに光明に包まれておばあさんと一緒に新年の喜びをお祝いしに行ったのかを知っている人は誰もいませんでした」。
この話はキリストを信じていた少女が、みじめにこの世を去ったというお話ではない。
一番良いところに行ったというハッピーエンドとして、アンデルセンはこの話を書いた。
マッチ売りの少女は、小さな者が大きくされたというお話。
そうは言っても、生きている間は辛かったと思ってしまうが、生きている間幸せでも、その後、神の元に引き上げられないなら、それこそ救いがない。
何より、マリアのお腹に宿ったイエスの一生はどのようなものだったか。
生まれる前から、苦難の連続。
マリアが身ごもったのは結婚前。
誰がどう見ても、マリアがヨセフを裏切ったとしか思えない状況。
一歩間違えれば石打ちの刑で死刑。
生まれた場所は馬小屋。
ある牧師がこう言った。
「私は、自分がもし馬小屋で生まれたとしたら、そのことを一生誰にも言わなかっただろう」。
大人になって神の働きをするようになっても、権力者にとことん憎まれた。
挙句、十字架。
イエスの生涯だけを見て、それだけで、イエスが幸せだったと言えるだろうか。
普通に考えてそうは言えない。
それでもイエスは神と人を愛しつづけた。
イエスは、人を神の元に引き上げるために、自分が十字架にかかる、自分が人の代わりに裁きを受ける、そのためにこそ、この世に来てくださった方だから。
そのために、大きな方が、小さくなってくださった。
イエスにとってはそれこそまさに、生きている間幸運に恵まれていても、死んだ後神に見放されるのなら、意味がない。
というより、イエスにとってはそれがすべて。
そのために命を投げだすのだから。
そこにすべてをかけている。
それなのに、もし、生きている間幸運だったから、死んだ後もそうだろうと思うのなら、それこそ、今日の言葉で言うところの思い上がり。
今生きている私たちにとっては、生きている今が本当で、死んだ後の方がファンタジーのような気分になるが、神の元から来た神の子イエスにとっては、死んだ後の方がほんとう。
アンデルセンはそのようなイエスの感覚を良く分かっていたのではないか。
マリアも、良く分かっていたと言える。
結婚前に身ごもった。
これほど大変なことはない。
自分の命がいつまであるか分からないような状況。
しかし、この時のマリアは、よほど喜んでいたのではないか。
何しろ、56節を見ると、三か月滞在した。
マリアはごく若い人。
それが、自分の家を出て、親戚のところに三か月もいた。
何のためにここにいたのか。
エリサベトと喜びを分かち合っていたのだろう。
三か月間も話すことが尽きないくらい。
それくらい、マリアは、自分の主人である神様が自分の面倒を見てくださる、だから、大丈夫だと信じ切っていたのだろう。
これも、私たちに当てはまる。
私たちも幸いな者とされた時、喜びをいつまでも分かち合うようになる。
自分を小さくすれば、神様に喜びを大きくしていただける。
その喜びを私たちも互いに分かち合いたい。
クリスマスの季節、教会がそのような場であってほしい。