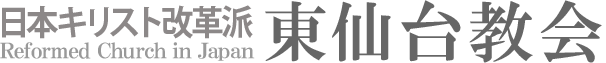時代から救われよ
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 使徒言行録 2章37節~42節
37人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロとほかの使徒たちに、「兄弟たち、わたしたちはどうしたらよいのですか」と言った。38すると、ペトロは彼らに言った。「悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を赦していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。39この約束は、あなたがたにも、あなたがたの子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、わたしたちの神である主が招いてくださる者ならだれにでも、与えられているものなのです。」40ペトロは、このほかにもいろいろ話をして、力強く証しをし、「邪悪なこの時代から救われなさい」と勧めていた。41ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に三千人ほどが仲間に加わった。42彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
使徒言行録 2章37節~42節
明けましておめでとうございます。
新しい年になりました。
例年、その年の最初の礼拝では、その年、一年の標語となる個所からの説教をしていますが、今年は使徒言行録2章40節のペトロの言葉を選ばせていただきました。
「邪悪なこの時代から救われなさい」という言葉ですね。
なかなかショッキングな言葉ですが、時代というものはその時代その時代の人間の意識が作っているものですので、いつの時代でも、そもそもそんなに良いものではないわけです。
まあそんなことは誰でもそう思っていることでしょうが、聖書では「時代からの救い」ということが言われることはまれで、それよりも「罪からの救い」ということがもっと多く言われますね。
ただ、時代というものを作っているのが人間であり、人間は罪ある者ですから、結局は、「時代からの救い」ということも、「罪からの救い」ということも、突き詰めると同じことを言っていることにもなるでしょうか。
気を付けなければいけないのは、私たちは、いつの時代でもそんなに良いものではないということを知ってはいても、その事実に目をつぶってしまっていることがあるということです。
世の中そういうものだと、勝手に納得してしまっているところがあると思うんですね。
あるいは、世の中そういうものだということが私たちの無意識に刷り込まれてしまっていることもあるのだと思います。
20世紀のフランスにロラン・バルトという哲学者がいまして、その人は、世の中全体で無意識にそうなってしまっているというようなことについて、それを「現代社会の神話」と呼びました。
私たちも、何かの形で「現代社会の神話」を刷り込まれてしまっているということになるのでしょう。
もし、何百年後の人たちが、今の私たちを見たとしたら、どう見えるでしょうか。
この時代の人たちはおかしな考えに縛られていたんだなあと思うに違いありません。
それは私たちが、何百年前の時代の人たちを見て、この時代の人たちはおかしな考えに縛られていたんだなあと思うのと同じことです。
いずれにせよ、人間はいつの時代も、その時代その時代のおかしな神話を刷り込まれていると言えます。
そして、それは無意識でのことです。
意識して考えて検討して選択したことではなくて、それはそういうものなんだというようなこと。
私たちが何百年前の時代の人たちを見て、この時代の人たちはおかしな考えに縛られていたんだなあと思ったとしても、その時代の人たちにとってはそれは当たり前のことであり自然なことであり、それしかないことだったわけです。
だから、検討もされない。
では、私たちはこの時代の中で、「現代社会の神話」の中で、どうすれば良いのでしょうか。
今日の場面の最初のセリフは、ペトロの説教を聞いた人々の言葉ですが、「兄弟たち、わたしたちはどうしたらよいのですか」というものですね。
この人々の「どうしたらよいのか」というのはかなり深刻な問いです。
なぜなら、ここまでペトロは長い説教をして、その締めくくりに、「あなたがたが十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、またメシアとなさったのです」とまで言ったからです。
それを受けて、人々は、「わたしたちはどうしたらよいのですか」と言ったんですね。
あなたがたが殺したイエスはメシアであるとペトロは言いました。
メシアというのは神からの救い主のことで、いつかやってくるということが旧約聖書に繰り返し預言されていて、しかも、この時代から400年も前から、神の言葉が人に降って人々に新しく伝えられるということがもう無くなってしまっていましたから、人々は神からの最終的な答えとして、昔々から預言されていた救い主を待ち望んでいました。
その救い主を自分たちが殺したというのなら、それこそ、これからどうしたらよいのでしょうか。
この時、ペトロの説教を聞いていた人たちは、もともとこの町、エルサレムに住んでいた人たちもいましたが、世界中の色々な所に住んでいるユダヤ人たちも、この時、エルサレムに来ていました。
この時は五旬祭というお祭りの日だったからです。
五旬祭はエルサレムで祝うお祭りでしたから、遠くからも人が出てきていたわけです。
そして、この時の50日前が過越祭というお祭りでした。
キリストはその時に十字架につけられました。
そして、過越祭もエルサレムで祝うお祭りでしたから、その時も、色々な所から人が来ていたわけです。
ですので、今日の場面でペトロの説教を聞いた人たちの多くは、キリストが十字架につけられた時もエルサレムにいたことでしょう。
ですから、ペトロがこの人々に対して、あなたがたが救い主を殺したというのは分かります。
キリストが十字架につけられた時には、エルサレムの人々は、イエスを十字架につけろと叫んでいたからです。
ただ、不思議なのは、ペトロの説教を聞いた人たちのこの反応です。
「わたしたちはどうしたらよいのですか」。
これは、イエスが救い主であると認めたからこその言葉です。
しかし、この人たちは、50日前には、イエスを十字架につけろと叫んでいた人たちです。
そして、どうして十字架につけろと叫んだのかというと、イエスが救い主ではないと見なしたからです。
救い主ではないのに救い主だと名乗ったから十字架につけろと叫んだんです。
その人たちがどうして、ペトロの話を聞いただけで、考えを変えたのでしょうか。
ペトロはこの時、旧約聖書を引用しながら適切に話をしましたが、イエスが救い主だと信じていない人に対して、旧約聖書のこの言葉はイエスのことなんですよと言ったところで、それで考えを変えるとは思えません。
ただ、この時には、弟子たちに聖霊が降って、弟子たちが行ったこともない色々な国の言葉で話をしだしたという奇跡が起こっていました。
その場にいた人たちの中には、それが奇跡だと信じる人もいれば信じなかった人もいたわけですが、奇跡が起こったと認めるのなら、聖書では奇跡というのは神の働きのしるしですから、その人の言葉に耳を傾けるのは当然だということになるでしょう。
そして、何よりの奇跡は、この時のペトロの話です。
教育らしい教育を受けたわけではないペトロが、聖書を自在に引用しながら、自分の考えを展開しているんですね。
つまり、この時、人々が考えを改めたのは、聖霊の力を目の当たりにしたからだとまずは言うことができます。
ただ、これはキリスト自身も言っていたことですが、奇跡を見たら人は信じるようになるのかというと、そうでもないわけです。
むしろ聖書では、奇跡を見ても信じなかった人の方が多いのです。
ペトロの話はしっかりとした話でしたが、それにしても、「あなたが殺した」とまで言われたら、それをすんなりと受け入れることができるでしょうか。
救い主だとは知らなかったから仕方なかったんだと、言い逃れできそうなものです。
また、ペトロは話の中で、キリストの復活について長い話をしていますが、話を聞いていた人たちのほとんどはキリストが復活したことを知らなかったはずです。
復活したキリストが500人以上の弟子たちの前に姿を現したということがコリントの信徒への手紙一に書かれていますが、それは弟子たちの前に現れたということで、弟子でない人の前には姿を現したことはなかったようですし、仮に赤の他人の前に現れたとしても、その人がキリストの外見を知らなかったら、復活したという認識にはなりません。
つまり、ペトロの話を聞いていた人たちは、キリストの復活という、この人たちからすれば信じなくても良い話をも信じたということになります。
これは、聖霊の力がペトロだけでなく、話を聞いている人たちにも及んだということでしょう。
普通に考えるとありえないことが起こったのです。
同じ力が、私たちにも及んでいます。
私たちも、今日の人々と同じです。
信じなくても良い話を信じているわけです。
否定しようと思えばできる、言い逃れしようと思えばできる話を、自分のこととして受け止めているんです。
そう、大事なのはそこですね。
この人たちも、自分のこととして受け止めていたんです。
だから、「わたしたちはどうしたらよいのですか」と聞くんですね。
しかし、救い主を十字架につけたという罪は小さなものではありません。
というより、それ以上に大きな罪を想像するのも難しいくらいです。
その罪というものも、この人たちのことだけではありません。
私たちにしても同じです。
救い主が十字架にかかってくださったのは、人の罪に対する罰を肩代わりしてくださったということであり、だからこそキリストは私たちの救い主なのであり、また、だからこそ、逆に言って、今ここにいるこの私たちの罪が救い主を十字架につけたということにもなります。
ただ、それでも、「わたしたちはどうしたらよいのですか」と聞いて良いのです。
取り返しのつかない大きな罪が指摘されてはいますが、その私たちの罪に対する罰を、キリストが代わりに受けてくださったからです。
私たちも、取り返しがつかないようなことになってしまったとしても、絶望する必要はありません。
その私たちのために、救い主はいらしてくださったのです。
どうしたらよいのかという問いに、ペトロは、「悔い改めなさい」と答えました。
「悔い改める」という言葉は原文では「帰る」という言葉で、神から離れていたことろから神に立ち返ることを指す言葉ですが、ここで大事なことは、「悔い改めれば赦される」とは言われていないということです。
ペトロは、洗礼を受け、罪を赦していただきなさいと言っています。
洗礼とは罪を洗い清める儀式ですが、洗礼を受ければ、神が赦してくださるということです。
神に立ち返るという私たちの心の中でのことが決定的なのではなく、洗礼を受けることが決定的なことなんですね。
私たちの心の中でのことは何も決定的ではありません。
キリストが逮捕される前、ペトロは、「あなたのためなら命を捨てます」と宣言しました。
その決心はほんの数時間で覆ってしまいました。
私たちの決心は決定的なものではありません。
洗礼を受けることが決定的なことです。
その洗礼が、キリストの名による洗礼だからです。
「名」というのは、日本語には「名は体を表す」という言葉がありますが、名前というのは存在そのものを指します。
キリストの名による洗礼はキリストご自身による洗礼です。
私たちがキリストを十字架につけたのに、キリストご自身がその罪を洗い清めてくださるのです。
これはとほうもないことだと思われますが、それでいいんです。
キリストはそのためにいらしてくださったからです。
そして、「そうすれば、賜物として聖霊を受けます」と言われています。
ペトロ自身、聖霊を受けたからこそ、神の力が働いて、ここまで話すことができたわけです。
そしてそれは、約束されていたことだったということですね。
キリストが弟子たちに約束してくださった通りになっているということですね。
ですから、今はもうキリストは弟子たちのそばにおられませんが、ペトロは確信をもって人々に約束することができます。
「この約束は、あなたがたにも、あなたがたの子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、わたしたちの神である主が招いてくださる者ならだれにでも、与えられているものなのです」。
ここで一番大事なことは、神の招きこそが救いの根拠だということです。
地上におられた時のキリストもそうでした。
罪深いと思われていた人たちにご自分から声をかけました。
弟子たちにしても、キリストが声をかけてくださって、弟子になりました。
神は人を招いてくださる方だということです。
その招きに答えるのが、悔い改めということ、神に立ち返るということです。
ただ、神の招きに答えるのに、神に立ち返らなくてはならないとするなら、逆に言って、普段、人は、神に背を向けて生きているものだということになります。
聖書ではそれが罪ということなのですが、ペトロはここで、「邪悪なこの時代から救われなさい」と言います。
キリストご自身も、今の時代は悪い時代だと言っていました。
そして、そのような時代の者たちはしるしを欲しがると言われていました。
しるしというのは神のしるしとしての奇跡のことですね。
それを欲しがるというのはどういうことか。
証拠を見せろということですね。
しるしを見せてみろ、見せればこちらで、それが本当に神のしるしかどうか、判断してやるよということです。
それはもちろん神よりも自分の判断を上に置いているから言えることであり、そのような考え方がキリストを十字架につけたとも言えますが、それはキリストの時代、ペトロの時代だけのことでしょうか。
人間というものはそういうものなんだと思います。
聖書も、人間というものは罪人だと言っているわけです。
そして聖書は、人間は自分の罪を自分ではどうにもできないとも言っています。
これは、人間が自分の判断を一番にしてしまうということも同じではないかと思います。
実際、私たちは自分の判断を第一にして生きることしかできない者で、時に自分の間違いを認めることがあったとしても、自分の判断が第一であること自体は変わることがありません。
私たちにとって自分の判断が第一ということは、私たちが考えて検討して選び取ったようなことではなく、もう無意識にそうなっていると言えるでしょうか。
無意識にそうなっているのなら、タッチすることはできません。
無意識にそうなっていることというのは、当たり前のことであり、自然なことであり、それしかないことです。
ロラン・バルトという哲学者は、世の中全体で無意識にそうなってしまっていることを「現代社会の神話」と呼びましたが、時代を超えて、いつの時代も私たちは、自分の判断を第一にして、自分を神にする神話を生きていると言えるでしょう。
そのような者である人間というものを、聖書は罪人だと言っているのです。
しかし、そのような人間を神は招きます。
この日に三千人が洗礼を受けたとあります。
この三千という数字はものすごく多いという意味であって、実数ではないとも言われますが、とにかく、ものすごく多くの人が招かれたわけです。
そして、その人たちは、変えられました。
今まで熱心でなかったことに熱心になったんですね。
自分の判断が第一で、自分を神にしようとするというところから、少なくとも意識の上では、違うところに導かれていったわけです。
それが、「使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること」ですね。
これに熱心になることが、自分を神にしようとしないということです。
まず、「使徒の教え」というのは説教のことです。
これは、使徒たちが自分の考えを教えたということではなく、使徒たちというのはキリストとずっと一緒に居た人たちということですから、使徒たちを通してキリストの言葉を教わったということでしょう。
どんなことでも聞くことから始まります。
ただ、それだけで完結するということではないんですね。
次の「相互の交わり」というのは単なる人との付き合いではなく、一つになって共にあずかるというような深い意味の言葉です。
キリストの言葉を聞いて、それを聞いた人同士で恵みを分かち合うことだと言えるでしょうか。
そうして、パンを裂くこと、これは聖餐式ですね。
キリストがそのようにしなさいとおっしゃっておられたように、パンとぶどう酒を、私たちのために裂かれたキリストご自身の肉、私たちのために流されたキリストご自身の血として、キリストの命に共にあずかる、分かち合う。
そして、その流れの中で神に祈るんですね。
これらは、自分を神にしようとする方向性とは正反対の方向性を持っているものだと思います。
そしてそれらは今も、教会にとって中心になっていることです。
私たちも意識して、これらのことを大切にしたいですね。
何しろ、救い主を殺したとまで言われた人たちが悔い改めて、心の向きを変えた結果、熱心にしていたことが、これらだったと書かれているんです。
これでいいんだということです。
これでいいんです。
むしろ、自分の罪を自分でどうにもできない私たちに、これ以上のことはできません。
そして、自分の罪を自分でどうにもできないからこそ、キリストが来てくださったのです。
だから、「使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること」に熱心になる。
その中で、聖霊の働きがあり、教会が大きくなっていくということなんですね。
それが、今日の御言葉の約束であり、キリストの約束です。
その約束の中で、私たち自身ここに招かれているんです。
そして、「使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること」、そのすべてが、今日の私たちの教会にあります。
一年の最初のこの礼拝に、熱心でありたいと思います。
神様が私たちの教会に、ますます聖霊の御力を豊かに現してくださいます。