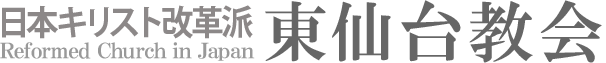何を誇るか
- 日付
- 説教
- 尾崎純 牧師
- 聖書 ローマの信徒への手紙 5章1節~5節
1このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、2このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています。3そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、4忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。5希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。日本聖書協会『聖書 新共同訳』
ローマの信徒への手紙 5章1節~5節
今日取り上げた御言葉はとてもよく知られた御言葉なのではないかと思います。
特に今日の3節4節5節は人類の歴史の中でどれくらい多くの人たちを励ましてきたでしょうか。
私自身、この言葉には何度も励まされました。
今日はこの御言葉を共に味わいたいと願っています。
この御言葉に立って、皆さんに希望を生きていただきたいからです。
さて、パウロは今日の1節で、「わたしたちは信仰によって義とされたのだから」ということで話を始めます。
信仰によって義とされる。
義という言葉は「神の前に正しい」という意味になります。
私たちは、信仰によって神の前に正しいとされた。
ということは逆に言いますと、私たちはもともとは神の前に正しくなかったわけです。
1節の後半に入ると、私たちは今は「神との間に平和を得て」いる、と話が続いていきますが、もともとは神との間にも平和がなかったんですね。
これは私には良く分かることなんですね。
信仰を持たなかった頃、神というものが何であるのか、そもそもそれを良く分かっていませんでしたけれども、とにかく、平和がなかったんですね。
もちろん、誰かとの関係が平和だ、とか、自分が置かれている環境がその時は平和だ、ということはあったんですが、誰かとの間に平和がある一方で、誰かとの間に平和はありませんでした。
また、自分が平和な状況に置かれていることがある一方で、平和でない状況、平和でない時期も多かったんですね。
というよりも、平和でない時期の方が多かったんです。
ですので、そもそも神が何なのか分かっていなかったわけですが、その時、神との間に平和があるかと聞かれたとしたら、そんなことは絶対にないと言い切ったと思いますね。
しかし、考えてみますと、信仰をもって生きるようになってからも状況はある意味同じなんですね。
平和な時期は少ないですし、人との関係も平和でない関係というのはあります。
ただ、今は決定的に違うことがあるんですね。
それは、「神との間に平和を得ている」ということです。
状況がどうであろうと、人がどうであろうと、私と神との間には平和がある。
この、「神との間に」という言葉は、「神の前に」という言葉です。
私は神の前に安心して立つことができる。
これですね。
私たちは神の前に安心して立つことができる。
自分よりもはるかに大きな神の前に、安心して平和な心で立つことができる。
私は神に受け入れられている。
これがないなら大変ですよ。
私たちは身の回りの状況にゆるがされてしまう。
人間関係にゆるがされてしまう。
そういうことは今でもあるわけなんですが、しかし、私たちはどれだけゆるがされたとしても、神の前に立つ者である。
神に向かって真っすぐに立つ者である。
キリストのたとえ話にありましたね。
家を建てる時、砂の上に建てるなら、洪水になると家は倒れてしまいます。
しかし、地面を深く掘り下げて、岩の上に土台を置いて建てるなら、ゆるがされることはないんですね。
私たちは、何よりも確かな土台の上に立っているんです。
2節に入ると、そのことがまた別の言葉で言われています。
私たちは「キリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ」たということですね。
これは1節の後半を言いかえたものですね。
神との間に今、平和を得ている。
それが、今の恵みということですね。
今、私たちは恵みの中に導き入れられている。
神は恵みの神。
神の前に平和に立つことこそが私たちを確かなものにする恵みなんですね。
そして、それは「キリストのお陰」であると言われています。
1節にも、「イエス・キリストによって」という言葉がありました。
私たちの努力によってではないんですね。
神の子キリストが私たちのところに来てくださって、私たちを神にとりなしてくださった。
だから私たちは神の前に立つことができるものとされた。
この1節と2節には「信仰によって」という言葉も繰り返し出てきていますが、これも同じことですね。
気を付けていただきたいところですが、これは、信仰という私たちの精神的な努力によってということではありません。
私たちの努力によってではないんですね。
キリストが私たちを神の前へと招いてくださっている。
それを受け入れることが信仰ということです。
ですからこれは、何か私たちが高度な精神修養を積んだとか、そういうことではないんですね。
感謝して招きにこたえるか、招きをこばむか。
私たちはこばまなかったんですね。
それだけです。
1節の最初に「わたしたちは信仰によって義とされた」という言葉がありましたけれども、私たちの誰が、自分が神の前に正しいと言えるでしょうか。
これはパウロが繰り返し言ってきたことですけれども、私たちの誰も、神の目に正しい者ではないんですね。
知っていて犯す罪があります。
おそらくそれ以上に、知らずに犯している罪があります。
それでも、私たちは信仰によって義とされた。
神がそれでもなお私たちを愛してくださって、私たちをみもとに招いてくださって、私たちは神の前にこうして進み出た。
これは逆に言うと、私たちは自分の力では何もできない者であるということです。
私たちは、神に正しいと認めていただけるようなことは何もできない。
だからこそ神が私たちを招いてくださるんですね。
そして、だから今、私たちは神の前に確かなんです。
また、私たちが確かにされる神の恵みは現在だけのものではないんですね。
未来にも及びます。
2節の最後ですが、「神の栄光にあずかる希望」とありますが、希望というのは未来のことですね。
私たちが神の栄光にあずかるのは、私たちが未来に、神のみもとに行く時のことです。
現在だけでなく、未来にも希望がある。
私たちの生き死にを超えて、私たちは神の前に立ちつづける。
どんなものも、私たちを神の前から引きはがすことはできない。
だからこそ、3節ですが、苦難も誇りとすることができるんですね。
ここに見られる苦難という言葉は、信仰があるからこその苦難を表す言葉です。
私たちは信仰があるからこそ苦しむことがあります。
この手紙が書かれた時代には迫害ということがありましたし、そういうことがなかったとしても、信仰があるからこそ、信仰がなければ気にしなかったようなことを気にして苦しんでしまうということは誰にでもあると思います。
しかし、信仰に立っているからこその苦難は、苦難では終わらないんですね。
私たちはそのような苦難を通してきたえられるんです。
ますます神様に近づくんです。
ここに出てきます「忍耐」という言葉も、「練達」という言葉も、信仰の上でのことです。
「忍耐」について言いますと、イエス様の言葉に、「最後まで耐え忍ぶ者は救われる」という言葉がありますね。
「練達」という言葉については、これは精錬するという言葉なんですが、金属が火によって精錬されるように、信仰がきたえあげられることを指す言葉です。
信仰があるからこその苦しみは、私たちが耐え忍んでふみとどまる力を身に付けさせ、私たちを鍛え上げるんですね。
それによって私たちはますます希望を確かにされるんです。
ますます神の前にまっすぐに立つ者となるのです。
苦難というものは、好ましものではないと思われるかもしれません。
しかし、苦難無くして、練達に至るということはありません。
私たちは皆、それを知っているはずです。
苦難は必要なものです。
私が小さい頃、蝶の繭を見つけたことがありました。
その繭に、ある日、小さな穴が開きました。
私は、蝶がその小さな穴から自分の体を押し出そうともがくのを、ずっと座って見ていました。
私の目には、蝶が苦しんでいるように見えた。
そこで、私は蝶を助けることにしました。
ハサミで繭の残りの部分を切り落としたのです。
すると、蝶は簡単に出てきました。
しかし、体はむくみ、羽は小さく縮こまっています。
今にも翅が大きくなって体を支え、やがて飛ぶだろうと思い、蝶を見続けました。
しかし、そうはならなかったのです。
蝶はいつまでも、胴体を膨らませ、羽を縮ませたまま這いずり回るしかできませんでした。
私は理解していませんでした。
蝶が繭の小さな隙間から出てくるのに苦労するのは、蝶が繭から出たときに羽ばたいて飛ぶことができるように、蝶の体から翅に向けて体液を押し出すための、神の定めた方法だったんです。
もし、神が私たちに苦難のない人生を歩ませるなら、それによって私たちはある面、不自由にされることでしょう。
私たちは、本来あるべき姿ほど確かにはされないでしょう。
それはまるで、繭を切ってもらって出てきた蝶のようなものです。
それは、神の方法ではありません。
神の方法は、忍耐から練達へ、そして希望へと進ませるものなんです。
そして、その希望は裏切らないんです。
5節ですが、「わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです」。
私たちにはすでに、聖霊が与えられている。
洗礼を受けた時に、神の霊が与えられている。
私たちは神の前に立っているだけではなくて、私たちの中に神がおられる。
聖霊は神の愛を注ぎます。
神の愛はどんなものですか。
何もできない私たちをご自身のもとに引き寄せてくださる愛です。
私たちは何もできなくていいんです。
というより、苦難にあって私たちにできることは実際のところほとんどないと言ってもいいのではないでしょうか。
それでも、神は私たちの内におられる。
神が私たちの内に働く。
神の愛を注いで、私たちをますます神に引き寄せる。
そう信じるなら、苦難は理由のない苦しみではなくなります。
私たちは苦しみの中でも希望に生きる訓練を受けていることになるのです。
人の目に希望が見えないような状況というのはあります。
しかし、私たちはそこでもなお希望を生きる。
神が私たちの内におられるから、私たちにはそうすることができると言われているのです。
もうこれは普通の生き方とは全く違う生き方です。
パウロは、2節3節で、誇りということを言いますね。
希望を誇りにする。
苦難をも誇りとする。
しかし、希望というのはまだ実現していないことです。
それは、誇ることができるようなものではありません。
まして、苦難というものは誇るようなものではありません。
もとより、パウロほど人間の誇りを否定した人はいません。
ということは、どういうことになるのか。
パウロはここで、自分を誇るなと言っているんです。
自分を誇る代わりに、神の栄光に与かる希望に心を向けなさい。
自分を誇る代わりに、苦難を通して信仰が高められることに心を向けなさい。
私たちは何もできない者だからこそ、キリストによって義とされ、平和を与えられ、恵みに入れられたんです。
人間は神の前では何も誇ることはありません。
パウロは、かつては自分を誇る人であったことでしょう。
パウロはユダヤ人たちの中でエリートでした。
しかし、パウロはその、自分の誇りをすべて捨てた人ですね。
自分の誇りを捨てたからこそ、何もできない私たちを救う神の愛を、自分のこととして本当に喜ぶことができる。
信仰に入った者は、もうこの世の側にいないんです。
神の側にいる。
神の側に生きている。
誇るというなら、それを誇るということなんです。
そしてそれは、実際のところ、それ以上ないくらい、誇らしいことではないでしょうか。
「わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれている」。
それ以上のことがあるでしょうか。
無いんです。
この世では自分を誇ります。
自分の成し遂げたことを誇ります。
それはそれで、悪いこととも言えないでしょう。
しかし、どれだけ大きなことを成し遂げた人でも、それだけ自分を誇っている人でも、「わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれている」ということ以上のことではないはずです。
私たちも、誇っていいんです。
私たちの神を、神の、私たちに対するなさりようを、誇りましょう。